ホラー作品における脚本づくりのポイント
暴力、超常現象、理不尽さ…白石監督が恐怖を感じるもの
白石監督は暴力に怖さを感じるといい、自身の作品にも度々登場させている。特に、登場人物が得体の知れない異世界の何かから突如、何事にも釣り合わないような不条理な暴力を受けるシーンが印象的だ。それゆえ、快楽のためだけに殺人を繰り返すシリアルキラーを描くようなホラーは興味の対象外で、映画で描く価値を感じないという。
戦慄怪奇ファイル コワすぎ!FILE-02 震える幽霊(2012年製作)

脳内でキャラクターが勝手に動き出すような脚本が理想
ご都合主義でキャラクターを駒のように動かしてはいけない
—ホラー作品にはさまざまな恐怖表現があると思いますが、白石監督にとっての“怖さ”とは何でしょうか?
私が映画に登場させて面白いと思える、あるいは描写したいと思える怖さというのは基本的に暴力的なものです。ポイントは理不尽さや不条理性だと思います。例えば交通事故ってすごく怖くないですか? 車という機械を使った突発的で理不尽な暴力…だから怖いんです。あと、不条理というものを拡大解釈して、この世にないものが、特別悪いことをしたわけではない人を襲う、とか。あるいはちょっとしたことをやっただけなのに、得体のしれない何かに殺されたり、消されたり…。これも暴力の延長線上にあると考えていて、私がよく描いている恐怖だと思います。超常現象が起こるホラー作品では、コズミックホラーと呼ばれるクトゥルフ神話的な宇宙的恐怖を描いています。とにかく得体の知れないものが異世界に存在していて、何かの拍子にそれが人間にちょっかいを出してくる、と。自分にはそれも暴力的なものに感じます。
—たしかに監督の作品によく登場するモチーフです。
同じ世界を共有していながら、人間の意思とは関係なく、宇宙の法則で隕石が降ってくることがある、という恐怖ですね。そこにすごくロマンがあって面白い。だから映画で描く価値があると思っています。一方で、“人間が怖い”という要素もありますが、フィジカルの奥に宇宙的な恐怖を抱えていてほしいと思っていて、“得体の知れない人間”であることの恐怖は好きでよく描いています。
—そういった恐怖を描くうえで、脚本の段階で大事にしていることはありますか?
脚本は序盤に気を遣います。“本物っぽさ”をたくさん入れようとしても、段取りみたいなことばかり起きてしまうと興醒めしてしまいますから。フェイクドキュメンタリーであれば、あくまで事故的に撮られた、と見えるように物語を進める必要がありますね。あと、自分は娯楽映画を作っている監督なので、ホラーに限らず“飽きずに最初から最後まで見れる”ということは意識しています。基本になっているのはハリウッド式の3幕構成で、『SAVE THE CATの法則』という本もありますが、このメソッドに従って脚本を書きますね。「〇〇の出発(〇分)」みたいにシーンまで分けたロングプロットをまず書きます。それを台本形式に落とし込むとすでに60ページ(60分ぶん)くらいになります。そこから、曖昧に書かれた部分を脚本形式にしていき、尺の想定と照らし合わせながら足し引きし、最終的に目標としている尺のページ数に調整していく、というやり方です。
—かなりロジカルに組み立てていくんですね。白石監督の作品には魅力的なキャラクターが多く登場しますが、どのタイミングで形づくりますか?
脚本を練っていくなかで、一番大切なのはキャラクターがどう動くかです。主要な登場人物が出揃わないと話が始まりませんから。なので、プロットを書くときに、このキャラクターはどんな性格だろうか、こんなキャラクターもいるといいな、と考えていきます。プロットを最後まで書き切ったらブラッシュアップの作業に入りますが、キャラクターを自分の都合に合わせて動かしてしまうと、駒のように動いてしまって、生き生きとしていないものになってしまいがちです。そこでのコツは、キャラクターが動くの待つ、ということ。私の作品ではキャラクターがいろんな危機に直面するシチュエーションが多いですが、そのときにキャラクターがどういう感情になって、どういう行動を取るのか…。それを常に頭の中で考えながら書き進めていくと、脳内で勝手にキャラクターが動き出すような感覚になるんですよ。自分が想像もし得ないようなことをキャラクターがしている、と。これには自分でもビックリすることがあります。「えっ! そんなことするの!?」みたいな(笑)。当然、すごく時間がかかりますし、自分が物語の中に入っていかないといけないので負荷はかかりますけど、キャラクターが勝手に動き出したら“生きている”証拠。そういう瞬間がたくさんあるといい脚本ですし、映画としても“勝ち”です。
—セリフは口調まで書かれるそうですが、役者が言い方を変更する余地は残すのでしょうか?
そうですね。自分がイメージしたキャラクターを脚本という文字で一度定着させて、文字の上でなるべく生き生きとするように作り上げますが、生身の役者さんがセリフやアクションとして表現するときに合わない場合も多々あります。それなら脚本を厳守させるより、現実の役者さんに馴染んだほうがキャラクターは生き生きするので、そこは現場などで調整していきます。
フェイクドキュメンタリーにおける“カメラマン”という役割
『コワすぎ!』シリーズで白石監督は撮影を担当しながら、カメラマン・田代役として出演もしている。「細かなカメラワークよりも役になりきることしか気にしていないです。それがリアリティのあるカメラワークにつながります」と白石監督は言う。実際に恐怖の現場にいるカメラマンとして、リアルな感情に沿って見せたいものを撮影するため、焦りや驚きで生じたボケやブレなどはOKとのこと。
戦慄怪奇ファイル コワすぎ!最終章(2015年4月15日劇場公開)
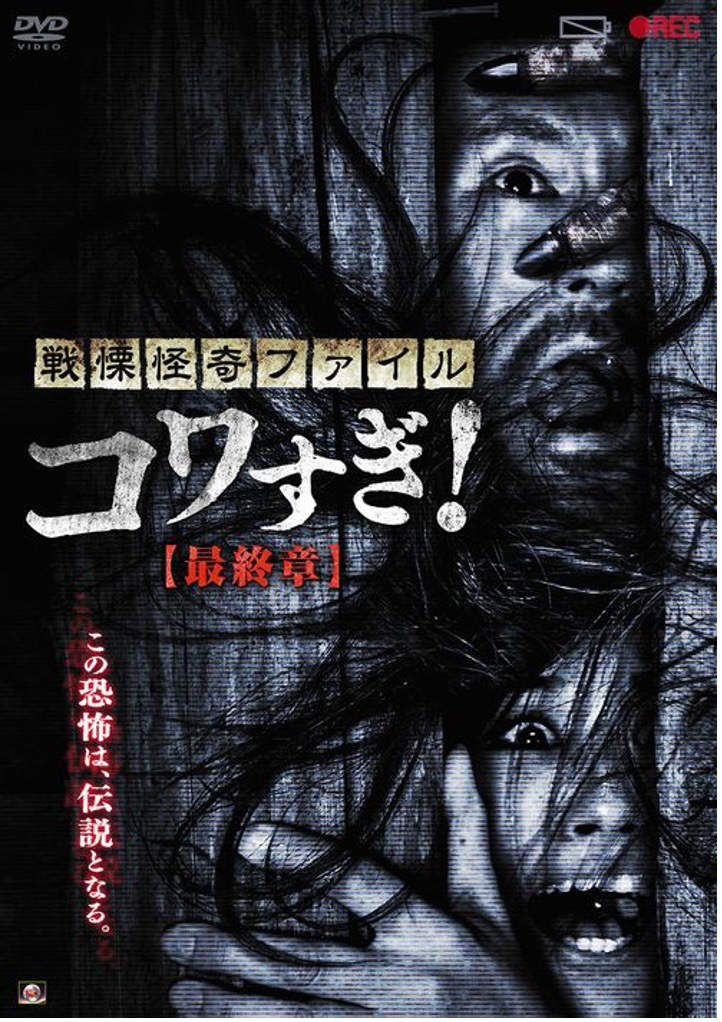
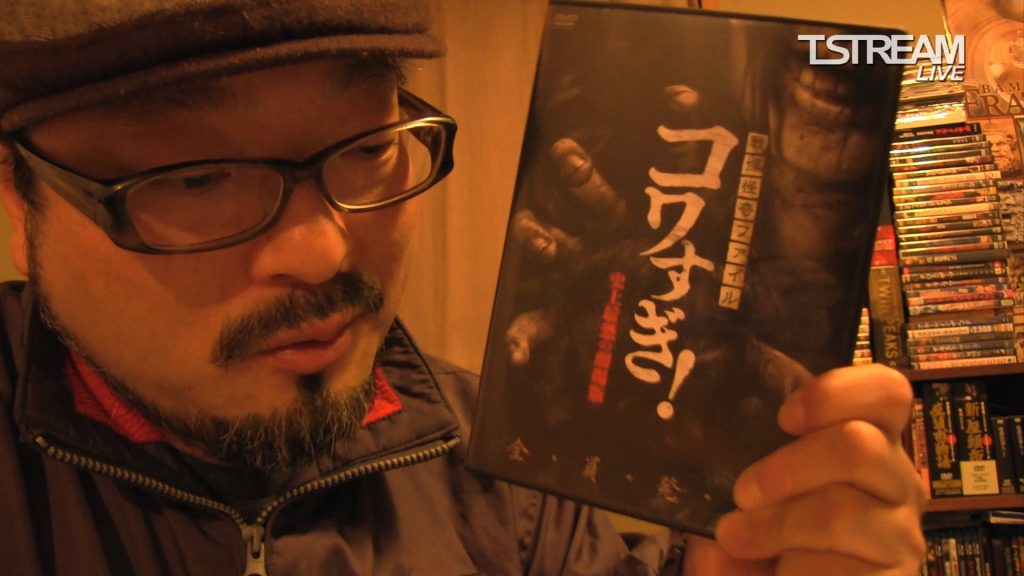

怖がっている側のリアクションをうまく映す
感情をしっかりと出さないと本物にならない恐怖のリアクション
役者のフィジカルから本当の恐怖が自然に出てくるようにする
—現場で意識していることも聞かせてください。怖いシーンをどのように撮っていくかという点について。
ホラー作品のキモは怖がっている側のリアクションをいかに映すかです。怖さのあまり黙ってしまったり、凍りついたりするリアクションもありますが、基本的に観客は怖がっている役者を見て、それがどれぐらい怖いことなのかを認識します。だから恐怖表現のシーンでは、まず怖がっている側のリアクションを見せて、それから怖いものを見せる、という流れが定石です。ここで大切になるのが怖がっている人のリアリティ。それがなければ、こちらが怖いとして提示したものを見ても観客は絶対に怖がってくれません。Jホラーでよくある“後ろに何かいる”というシーンでも、まずは役者が後ろにいるもの気配に気づいて怖がるリアクションを見せ、そのあとで背後の何かにフォーカスする、というのが基本です。
—リアリティのあるリアクションを役者から引き出すコツはありますか?
大きな悲鳴を上げたり、驚いて顔を歪めたりすることも大切ですが、それよりも怖いものが本当にいると思ってリアクションできているかどうか、です。うわべだけの怖がりの演技でやっていたら、観客は一瞬で冷めてしまいます。なので、本気モードで怖いリアクションが取れる人をキャスティングしたほうがいいです。大きな声を出すのであれば、声量だけではなくて恐怖の感情のリミッターも外して、本当に怯えることができれば理想的ですね。
—白石監督は怖がっている側のセリフを台本上で「きゃー」や「うわー」と書かずに、「(悲鳴)」や「(驚きの声)」としているそうですね。
毎回ではないですが、そのように書く場合もあります。例えば台本に「きゃー」と書くと、それをセリフっぽくただ「きゃー」と読んでしまう役者さんもいるんです。現実世界でも人が怖がるときはセリフで悲鳴を上げるわけではなく、感覚的に思わず声が出ちゃってるわけじゃないですか。役者には文字面にとらわれず、リアルなリアクションを出してほしい、ということです。その人の脳みそも含めたフィジカルから本当の恐怖が自然に出るといいな、といつも考えています。
—そういったリアクションをうまく映像に収めるために演出で心がけていることはありますか?
恐怖に限らず、感情を出すシーンの芝居は、役者は集中しないとできません。なので、なるべく集中できるような現場の環境は整えるようにしています。あとは、自分が役者のリアクションを見て本物だと思えるか、そしてその恐怖のレベルはこのシーンの恐怖のレベルに合っているのかを監督として見ています。リアリティがあっても、シーンに合っていない場合は、レベルの強弱を調整する必要がありますから。ホラーのようなジャンル映画は、人間ドラマよりも下に見られることが多いんですけど、ホラーのリアクションというのは感情をしっかりと出さないと本物になりません。だから人間ドラマと同じようにリアリティのある感情を出してもらわないといけない。しかも、この世に存在しないようなものに感情を出すというのはなかなか高度なことだと思います。
“本気のリアクション”を自然に出してくれる人をキャスティングする
戦慄怪奇ワールド コワすぎ!(2023年9月8日劇場公開)
芝居がうまい役者が必ずしもフェイクドキュメンタリーに向いているとは限らないと断言する白石監督。その哲学の一端が垣間見えるのが、シリーズの集大成ともいえる『戦慄怪奇ワールド コワすぎ!』。ノンストップで展開する恐怖シーンでは、キャストたちが“本気のリアクション”をごく自然に出しているように見える。


恐怖を増幅させる音響・劇伴とは?
映像として本物だと思えるような音の作り方・つけ方
フェイクドキュメンタリーでは暴力の音も“本物”でないといけない

戦慄怪奇ファイル 超コワすぎ!FILE-02【暗黒奇譚!蛇女の怪】(2015年7月11日劇場公開)
劇映画のアクションシーンでは多少デフォルメした効果音も許容されるが、臨場感を大切にするフェイクドキュメンタリーでは極限までリアルにこだわらないといけない。白石監督は暴力の音には細心の注意を払っているそうで、感覚的に「痛い」と思えない音にはOKを出さないという。一発の打撃につき、何十回もやり直すことがあるそうだ。
観客の感覚と音楽を一致させて徐々に恐怖を高めることが重要
—作品の音まわりで白石監督が実践しているテクニックがあれば教えてください。
臨場感を与えるということがひとつの重要なポイントです。劇映画一般でもそうですが、効果音や現実音によってクオリティに差が出ます。例えば紙を持ったときの「ぺらっ」という音、人物が屈んだときの衣擦れ、肌と肌が触れたときの「さっ」という音…。こういうちょっとした音を積み重ねることで、映像内の臨場感は倍増していきます。ホラー作品で特に大切なのは、見ている人の無意識にどう語りかけて、怖さを感じさせるか。私は相当細かく音のリアリティにこだわるほうだと思います。
—フェイクドキュメンタリーで音を特に気にするポイントはありますか?
音の“距離感”と“響き”ですね。これもリアリティを醸成する要素ですが、鳴っている音そのものだけでなく、どんな位置関係で鳴っているのか、あるいは音が反響している空間の質感まで感じられないと、フェイクドキュメンタリーなのにフィクション性が高くなって、作り物のようになってしまいます。音のリアリティがあるほど映像の本物感が高まるはずです。暴力シーンの音は特にリアリティを求めますね。ただ、フェイクドキュメンタリーもあくまでフィクションで、現実に人が誰かを殴ってもそんなに音はしないはずですが、映像として本物だと思えるような音は聴こえるようにしないといけません。だから効果音のスタッフは大変です(笑)。
—劇伴についてはどのように考えていますか?
劇伴の音楽は恐怖を倍増させる素晴らしい道具ですが、入れ方を間違えると興醒めになります。記号的に何度も繰り返し怖い音楽を押し付けられると、怖くなくなってしまうものです。やはり観客の感覚と音楽を一致させることがすごく重要で、気づかないうちに恐怖を高めてあげるぐらいのバランスの音楽の鳴り方にするのがいいと思います。考えるべきは音楽を入れ始めるタイミング。映像として恐怖の予感がするときは音楽を入れない、というのが定番で、何かが起き始めてしばらくしてから徐々に音楽を入れていく、と。予感の静寂と恐怖の絶頂で差をつけるほうが効果的だと思います。
白石晃士監督へのQ&A

脚本が煮詰まったときの解決法はありますか?
軽い監視状態を作るためにファミレスなど人がいる場所で書きますね。誰もいないよりはダラけてスマホに逃げる回数は減るはずです。あと、切羽詰まった状況でオススメな方法があります。まず誰もいない部屋で照明を消して真っ暗にしてください。スマホの電源は切って、ネットもなるべくオフラインにする、と。さらにヘッドホンかイヤホンで音楽を大音量で流します。なるべく“意味”が生じないインストものや他言語の曲がいいですね。この環境で、「全然書けない…」ではなく「いけそうだ!」というマインドで集中してPCの画面を見続けたら、2時間もあれば何か思いつくはずです。ただ、かなり疲弊します(笑)。

一度使ったアイデアを再利用することもある?
全然ありますよ。自分のオリジナル作品ではコズミックホラー的なアイデアやモチーフを多用していると思います。具体的な手法でも別作品でやり直すケースがあって、次はもっとブラッシュアップしてうまく撮れるはず! と思うからですね。例えば『サユリ』で階段の明かりがチカチカ点滅して人が現れたり、消えたり…という長回し風のシーンがあります。これは過去に『呪霊 THE MOVIE 黒呪霊』(04)という作品でやった手法をもう一度使ったものでした。あと、同じ声がループして聴こえるシーンや人がはねられる交通事故シーン、“霊体ミミズ”などは、自分の作品でよくやる手法だと思います。

魅力的なキャラクターを描くコツはありますか?
キャラクターがこちらの想像を超えることを言ったり、やったりするから魅力的に見えると思うんです。ただ意外性があるだけではなくて、そのキャラクターにとっては真っ当というか、見ていて納得できることが前提です。現実の世界でも仲の良い知人などが予想外の言動を取るときがありますよね? よくよく話を聞くとその言動に理由があったことが分かるわけですが、そういう感覚と同じで、作品の中のキャラクターが生きている人間だと捉えられることが大切だと思います。いかに“意外なこと”を思いつけるかが勝負ですが、自分の閃きには限界があるので、キャラクターが勝手に動くような臨場感のある脚本づくりがキモになってきます。

“令和のホラーブーム”についてどう思いますか?
今年は特にホラー映画の公開が多いですね。『変な家』(24)の凄まじいヒットが影響しているのかもしれません。あと、YouTubeなどで怪談や都市伝説が流行っていますよね。そのあたりとも関連して、大森時生さんが作られているようなリアルな手触りのある怖い作品が目立っているように感じます。ただ、自分は自分がやれることをやるだけですね。このホラーブームのなかで、もちろん他の人と違うことをやって目立ちたい、ヒットしたいとは思いますが、あくまで自分の思いつく、面白いと思えるものをやる、と。何を怖いとするか、という点において私は独自路線だと思いますので、これからもコズミックホラー的な恐怖を追求していきたいです。
戦慄怪奇ファイル 超コワすぎ!FILE-01【恐怖降臨!コックリさん】(2015年6月6日劇場公開)
白石監督の作品で有名なキャラクターといえば、『コワすぎ!』シリーズのディレクター・工藤とアシスタント・市川が思い浮かぶ。ふたりについて、監督自身も意外性のある生き生きした人間だとを思いながら脚本を執筆し、肉体を持った俳優が演じることでさらなる臨場感が加わっていると感じているそうだ。

新作『近畿地方のある場所について』での実践




原作の持つ本質的な魅力を活かすための映像的なアレンジ
「背筋さんの小説が原作になっていますが、原作をそのまま映画にすることはできません。小説はあくまで文字表現で、実写の映像表現とはまったく異なります。ただ、原作が持つ一番の魅力は絶対に損なってはいけない。リスペクトと共にそれを根っこに置きながら実写に変換していくわけです。例えば漫画原作であれば、必ずしも原作のキャラクターそっくりの役者さんをキャスティングしなくてもいいんです。漫画を読んだときのキャラクターの印象や感覚といったものを、実写でどう表現するかを考えるのが我々の仕事。“原作に忠実”というよりも、“原作が持つ本質に忠実”ということですね。本質に忠実であれば、映像化に当たって絶対に変えなければいけない部分がでてきます。『近畿地方のある場所について』の背筋さんは私の作品をよく見ていただいていたそうで、『ノロイ』からの影響も公言されていますから、こちらの“変換”について非常に理解していただけました。なので、今作では小説を読んだときの面白さや臨場感を大切にしながら、原作からかなり大胆にアレンジしています」(白石)
『近畿地方のある場所について』8月8日(金)から全国公開
<STORY>
オカルト雑誌の編集者が行方不明に。彼が消息を断つ直前まで調べていたのは、過去の未解決事件と怪現象だった。同僚の編集部員は、女性記者ともに彼の行方を探すうちに、恐るべき事実に気がつく。すべての謎は“近畿地方のある場所”につながっていた—。
<DATA>
監督・脚本:白石晃士 原作・脚本協力:背筋 脚本:大石哲也 撮影:高木風太 照明:後閑健太 録音:根本飛鳥 美術:安宅紀史、田中直純 VFXスーパーバイザー:浅川翔太 VFXプロデューサー:菊地 諒 音響:大塚智子 整音:田中 俊 編集:堀 善介 音楽:ゲイリー芦屋、重盛康平 主題歌:椎名林檎
